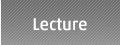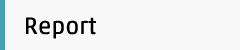UBEビエンナーレ会場風景 – ときわ公園内
1.はじめに
全国各地には、地元市民が主体となって身近な彫刻作品の維持活用をする活動が存在している。それらの活動は主に、1960年頃以降から各地公共空間で増加した彫刻の設置事業の後、彫刻の維持活用を趣旨とした市民グループが行政主導で形成されたケースが多い。私はその中でも立川市の市民グループであるファーレ倶楽部に所属しており、その他にも札幌、仙台、府中、清瀬、小平、大分などの活動に加わり、現地の彫刻作品に触れる機会を頂いてきた。いずれの作品も、私自身が生まれた頃か生まれる前に設置された彫刻作品ばかりであり、それらの作品の環境や市民活動、管理体制、設置の歴史もそれぞれの在り方があることを知った。そこには、専門家の中で彫刻が「彫刻公害」や「負の遺産」と揶揄された時代を越え、具体的な市民のコミュニティが洗浄やメンテナンスという活動を通して自身の街の彫刻に価値を感じている、という彫刻と市民との関係がそれぞれに築かれていた。筆者が訪れた地域の中でも、下記のグループは市民が主体的に屋外作品のメンテナンスの方法を作成し、学芸員や地元作家、修復家から専門的なアドバイスを受け定期的な活動を継続している。
札幌—札幌彫刻美術館友の会
仙台—彫刻のあるまちづくり応援隊
立川—ファーレ倶楽部
清瀬—キヨセケヤキロードギャラリーきれいにし隊
宇部—うべ彫刻ファン倶楽部
勿論、各地に多数設置された屋外の彫刻作品は様々な要因により破損や撤去の可能性を持ち合わせており、すべてが維持に十分な環境にはあり得ていない。もはや維持管理の問題は、現状の作品数の多さや素材の複雑性・専門性を考慮しても、上記のような市民のコミュニティや彫刻家ら専門家が、行政と連携して注視していかなければならない課題では無いだろうか。
そこで、昨年から今年にかけて宇部市のUBEビエンナーレとドイツのミュンスター彫刻プロジェクトに対し、現地取材する機会があった。双方ともに、芸術祭の開催とともに公共空間に彫刻作品を現在も残し続けている国内外の代表的なプロジェクトである。私はインタビューのみでなく、できるだけ多くの作品を鑑賞しようと市内を歩き回り、それぞれの街がその作品を維持してきたというエネルギーを現地で実感した。このレポートはUBEビエンナーレ2017とミュンスター彫刻プロジェクト2017の展覧会についてではなく、1960年代から急速に広がった屋外における彫刻作品の設置事業は今までどのように地域と寄り添ってきたのかについて、宇部市とミュンスター市の事例から、現地でこそ実感した大きな違いを踏まえて取材の内容を書き留めていく。
2.UBEビエンナーレ(現代日本彫刻展)
UBEビエンナーレは1961年から山口県宇部市の常盤公園で開催されているビエンナーレ形式の彫刻展である。1958年の戦後の混乱期(公害問題や空襲被害)の中で、緑化運動の予算の一部で購入されたEtienne Maurice Falconet の<ゆあみする女>(模造)が宇部新川駅前に設置されたことで、彫刻が駅を使用する市民の心を和ませた影響から「宇部を彫刻で飾る運動」が始まる。当時については美術評論家の柳生不二雄、竹田直樹らの調査に詳しいが、「宇部を彫刻で飾る運動」に参画していた当時の宇部市立図書館館長岩城二郎が、土方定一に助言を得たことで具体的に野外彫刻展が始まった。その後岩城や土方の他、当時の星出寿雄宇部市長ら行政関係者や柳原義達、向井良吉といった彫刻家、計16名が「宇部を彫刻で飾る運動」の中央運営委員として組織される。そして1961年から現代日本彫刻展(のちにUBEビエンナーレに改名)を2年に1度開催し、現在まで毎回の入賞作品を市のコレクションとして市内に設置し続けている。入賞審査には美術評論家、作家、宇部市市長などによって選考委員会が組織されており事前に公表がされている。 (屋内外のコレクション作品総数は400点を超え、屋外でも182点の彫刻作品を所有するに至る。)

Etienne Maurice Falconet <ゆあみする女(模造)>
現在、宇部市はビエンナーレの実施とともに、公園整備局の管轄のもとビエンナーレのアーカイブ、教育普及、広報事業が推進されている他、市民グループの「うべ彫刻ファン倶楽部」、「宇部市ふるさとコンパニオンの会」、「UBEビエンナーレ世界一達成市民委員会」の活動によって、市内の彫刻作品は維持活用されている。私は今回、宇部市渡辺翁記念会館・文化会館の山本麻紀子館長、宇部市文化創造財団の田中真由美さんに大変お世話になり、UBEビエンナーレの運営をされるときわミュージアムの学芸員である山本容資さん、また上記の3組の市民グループの皆様をご紹介頂いた。残念ながら、皆さんが一同に参加される彫刻メンテナンスの日に訪れることが出来たものの雨天により作業は中止となってしまったが、皆さんの温かいご対応によりそれぞれにお話を伺う機会を設けて頂いた。
半年に1度作品のメンテナンスを行う「うべ彫刻ファン倶楽部」、また作品のガイドを行う「宇部市ふるさとコンパニオンの会」は、それぞれの参加者に対し、直に作品に触り親しんでもらうことを重要視しているというお話が印象的だった。私は次回のメンテナンスこそ参加させてもらう予定だが、宇部市の彫刻が屋外の環境で年月を経てどのような変化を起こしたのかを実感することは、そのような機会に直接作品に触れることが大切なのだろうと思う。また「UBEビエンナーレ世界一達成市民委員会」の田村委員長は、「今後もUBEビエンナーレに入賞された作家さんに、入賞したことを誇りに思ってもらえ続けられると良い。」と話す。UBEビエンナーレやコレクション作品に関わる地元市民の皆さんから直接お話を聞けたことは本当に貴重だった。何より市民としての作品に対する熱量を感じさせて頂き、危うくそれのみで今回の取材に満足してしまいそうなほどだった。前回のメンテナンスには250名ほどの参加者が集まり、学芸員によって作業記録が取られているとのことだが、国内で最も歴史を持つ野外彫刻展のコレクション作品は、専門的な学芸員と大勢の地元住民とともに時を送り寄り添い合う体制の中にあることは間違いないだろう。なお、うべ彫刻ファン倶楽部のメンテナンス活動は2008年よりこれまで21回実施(21回目は雨天中止)されており、各回20点ほどのメンテナンスを行っている。作業内容こそ公表はしかねるが毎回作成されるマニュアルには、作品ごとに薬品が使い分けられるほど詳細な行程が見て取れる。

宇部市ふるさとコンパニオンの会、ツアーガイド下見の様子
3.ミュンスター彫刻プロジェクト
1977年から10年に1度、ドイツのミュンスターで開かれている国際的な野外彫刻展。現在でこそ世界的な認知がある彫刻展だが、1977年の初回は主にミュンスター市民への教育的意図を持つものだった。1976年、アメリカ人の彫刻家であるGeorge Rickeyの作品が市に寄贈されたことで世界大戦のトラウマを持った市民の中に議論を生んだことが、地元の州立美術館のキュレーターであったKlaus Bussmannに展覧会の必要性を感じさせた。Klausはそのような発端で現在も彫刻展のディレクターを務めるKasper Königとミュンスター彫刻プロジェクトを開始するものの、当初は長期的な計画を持っているわけではなかったという。
当時の行政が経済利益を理由に、カッセルで開かれる芸術祭「ドクメンタ」と同じ5年間隔、同年の開催を提案したところKasperは反対し、10年に1度というペースが彫刻と社会の関係また彫刻自身の変化を感じる上で適当と主張する。私は今回の開催で初めてミュンスターを訪れたが、この趣旨に共感しとにかく多くの作品に触れ、10年後の開催に向けてひたすら写真に収めた。出品作品とパブリックコレクションを含め70点以上の作品を鑑賞したが、観光者向けの自転車のレンタルサービスと、スマートフォン用のマップアプリがなければこれらの半分程度しかまわれなかっただろうと思う。(2017年の今回で第5回開催となるが、1977年に3点、1987年に21点、1997年に8点、2007年に7点の出品作品がミュンスター市によって購入、屋外に常設設置がされている。) 尚、ミュンスター市へパブリックコレクションの維持管理について取材をしたところ、パブリックコレクションは彫刻展の出品作品から専門家や市議会の関与を通して選出され、ミュンスター市によって体系的に管理されており必要に応じて年に1-4回の点検が行われているという。その点検で発覚したものかは不明だが、Martha roslerの2007年出品作品“Unsettling the Fragments(Eagle)”が偶然修復中であった。また、コレクションは都市計画、都市開発の中で重要な機能を果たしてきたとのことだ。

Martha rosler
ミュンスター彫刻プロジェクトは、前述した発端のエピソードを背景に一貫して「芸術と公共性」というテーマを持ち個々にメッセージ性を持つ作品が多い。地元の共有庭園の利用者に毎日綴らせた日記を展示するJeremy Dellerや、過去の保守的イメージが特徴的なミュンスターの街中でタトゥーショップを開くMichael Smith、反核デモの指導者Paul Wulfの像を製作したSlike Wagnerらの作品は特に印象に残った。これらの作品は実際に地元住民の参加によって成立しており、特に2007年製作のSlike Wagnerの作品は2017年までのPaul Wulfに関連した新聞記事が重ねて貼り付けられていることで成立している。一方で重要なことは、Kasperはいわゆる「街が美術館になる」ことに反対しており、彫刻展の前提として作品が永久的に存在しうる場所になってはいけないことを意味し、出品作家には作品の要素として時間性を重んじている。これは、上記の3名の作品もある一定の時間に生まれたものだからこそ価値を有している作品であるものだととらえて良いだろう。つまり今回のポイントとして、芸術と公共性を主題とした作品を観客に見せる彫刻展の主催側と、恒久的な常設作品を購入する行政側のスタンスは明らかに違うことが分かる。

4.まとめ
宇部市とミュンスター市においては、彫刻が公共空間に設置される経緯が彫刻展の主催者と彫刻の購入者(管理者)の関係を見ても異なることは確かである。それは、宇部市の「ゆあみする女」に期待を寄せた当時の行政/市民に呼応した土方定一と、“Three rotating squares”を問題視した市民を納得させることを試みたKlausとKasperの存在から大きく異なる方向性を持っていたように思う。さらには、第二次大戦の敗戦を経験した2つの地域であるにも関わらず、きっかけとなる彫刻への反応が双方で異なるという視点も可能だろう。
その他にも国内外の野外彫刻展を比較し、関連の市民コミュニティの有無や行政と主催者の関係など、異なることが多いことが分かった。しかし、宇部の市民が作品に直に触り維持をしながら親しんでいることと、ミュンスターのKasperが彫刻展の間隔にこだわりを持つことに共通するものを感じた。触れるだけでなく定期的に洗浄やメンテナンスという形で作品を深く観察し続けることも、10年という長い間隔で彫刻展が開かれることも、時間や環境とともに変化をする彫刻に人が関わるということなのだと再認識することが出来る。

Kasperと筆者
今回の2度の旅を通して、公共空間に設置された彫刻とは野外彫刻の一出品作品である前に、都市開発やまちづくりの要素である前に、作家によって作られた、私たちの生活と同じ次元で日々変化をする具体的な素材や概念的な要素によって構成された「作品」であると強く思わせられた。彫刻に寄り添うということは、彫刻の変化を感じ尊重することであり、その上で維持活用のような活動はされるべきなのだろうと思う。次回のうべ彫刻ファン倶楽部のメンテナンス活動と、10年後のミュンスター彫刻プロジェクトには必ず参加したい。
(文:高嶋直人)
高嶋直人 (Naoto Takashima)
1990年生まれ。静岡県出身。武蔵野美術大学造形学部芸術文化学科卒業。同大学造形学部彫刻学科黒川研究室清水多嘉示研究研究員。都内の他、札幌や仙台など各地の屋外彫刻やパブリックアートについて、市民活動の実践を交えながら作品の状態や活用方法などの調査を行う。ファーレ立川プロジェクトボランティアグループ、「ファーレ倶楽部」会員。屋外彫刻調査保存研究会運営委員。