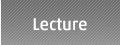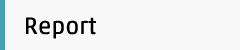2020年オリンピックイヤーが幕をあけた。東京では様々な文化イベントが予定されている。これは2012年のロンドンを参考にしていると言う。私は以前、ロンドンのNPOでコミュニティアートを実践する現場に数か月立ち会った。2004年当時は、オリンピック開催の最終候補都市に選ばれ、早くもカルチュラルプログラムが意識され始めていた。当NPOはイーストロンドンの、移民や低所得者層の多い地域にあった。地域の若者たちの文化的体験を支援しており、あるプロジェクトでは「NEW ROOTS- Young Hackney Voices」として音楽が好きな若者たちに対し、プロで活動するアーティストをコーチに迎え、詩をつくるワークショップから本格的な録音スタジオでの楽曲の収録、CDの制作、それをライブという場で表現するまでの機会を提供した。NPOのギャラリーで行われたライブには、区長や地域の人々が訪れ盛況だったが、ラップまじりのヒップホップを聞いて、涙を流すほどの衝撃を受けたのは私だけであっただろう。そこにはいわゆるマイノリティである彼らの「生きるための表現の場がある」と強く感じたのだ。アートが生き方の多様性を保障しているように見えた。

NEW ROOTS-Young Hackney Voicesライブの様子(2004年)

左:ライブの後は区長と若者たち、地域の人々が歓談 右:プロが立ち会い本格的に仕上げられたCD
さてここから農の話をしよう。「切り干し大根をつくる」と聞いて直ぐにアートのような創造性を、あるいはアートに触れたときのようなひらめきや高揚感を想像できるだろうか。

秋空の下で切り干し大根をつくる
2019年秋、北信州に住む私たちは切り干し大根を作るワークショップを行った。湖と森と山を抱く小さな町での小さな出来事だ。その日、自然農法で米と野菜を栽培する農家「りんもく舎」の畑に集まったのは、鍼灸師、絵本作家、元教師など数名。職種や働き方も様々な人間が集まり、畑から大根を引き抜き、水路で泥を落とし、空の下で包丁やスライサーを持ってひたすら大根を切る。ただそれだけのことだが、皆で手作業を共有すると普段はしない対話が自然と生まれる。
例えば、皆で昔の暮らしを想像してみる。保存食や伝統料理、その背景にある資源循環型の生活が当たり前にあっただろうことに話や想像は及ぶ。あるいは、そもそも切り干し大根を作ることとなった発端を自然農家とともに話し合う。出荷されずに畑に根付いたままの大根たち。自然農は農薬や肥料を使わないため、天候の変化による微生物の動きの影響を受けやすい。その結果、今年は大根の肌がきれいに仕上がらなかったというのがその理由だ。そこには気候変動も身近なものとして浮かび上がり、また、画一的に整うことが求められるスーパーマーケットの野菜たちの姿も、さらには学校教育のなかにある子どもたちの姿も重なってみえてくる。
この体験は、ひとつの作業や事柄を通して、多くの想像を引き出す、新たな視点を得るという点において、まさしくアートにおける体験と似たような感覚をもたらした。
 切り干し大根づくりの一連の作業風景
切り干し大根づくりの一連の作業風景
自然農の農家との対話では世界の真理の一端をみるようなことが起きる。ある時、畑の一角で団粒化した土を見せ、バクテリアの仕業なのだと教えてくれた。それは作物の栄養分を生成するバクテリアが生息し、住みやすい環境を生成していることを意味する。
「慣行農業ではいかに害となる菌を排除するかと考えるけれど、ぼくら自然農では、いかに多種多様な微生物を土のなかに生かすかと考えるんだ。多様な微生物が生息すれば一種だけが突出して繁殖し栽培に害を及ぼすということが起きないから。」と言う。彼の畑ではキノコも時折顔を出す。キノコ(糸状菌)が優位に働く土は自然のバランスが整っている証なのだと嬉しそうに話す。「土も草木も野菜も人も、それだけで生きている訳ではなく、いろんなものに生かされて生かし、持ちつ持たれつしながら生きている。単純、単一であることは効率的で便利かもしれないけれど、とても弱い。」ということを畑は教えてくれる。そして、多様性のある世界(土)がいかに美しく、その一部として育ち、共存する様々ないのち(野菜や雑草)の力強さを語ってくれた。
この対話を通して、彼がアーティストと同様な立場にあると感じた。アーティストはいわば世界の多様性を表す存在だ。定常化した社会の理を見つめなおし、異なる角度から表現し、私たちにあらゆる世界の在り方を提示してくれる。

左:枯草や稲藁の下で団粒化した土 右:キノコが生える畑の土 (りんもく舎提供)

自然農では野菜も雑草もいきいきと共存する (りんもく舎提供)
この自然農とアート、あるいは農家とアーティストの共通点は何だろうか。現在日本で自然農を含めた有機農家の割合は農家全体の0.5%に過ぎない。年々増加傾向にあるそうだが全国でわずか1.2万戸だ。(*1)一方アーティストの数は定義があいまいで計り知れないが、国税調査によると「文筆家・芸術家・芸能家」という社会経済分類で871,910人。(*2)ここで想定するアーティストの範囲はその中のさらに一部であるため、随分荒っぽい比較だが、少数派だと思われるアーティストと同様に、もしくはそれ以上に有機農家は極めて少ないことがわかる。有機農家もアーティストも選択的マイノリティとでも言おうか、オルタナティブな視点をもって社会を見てきた少数の人たちなのだ。彼らは今ある社会やシステムに違和を感じとり、ある人は自然農法という技法で、ある人はアートという表現方法で、問いを投げかける。それは藤浩志が自身の作品を「OS作品」というように、あるいは『藝術2.0』(熊倉敬聡著)のなかで小倉ヒラクが「OSとしてのアート」と表現しているように、OSの違いこそあれ、そこにある精神性や創造性という点で共通しているのではないか。そしてさらに言うならば、今まさにそれぞれのOSを持ち寄り、新たな価値を共有する、新たなOSを作り出すといった、いわば創造性の複合形がアートの文脈の内にも外にも増えつつあるように思う。
彼らは、多様性をもち、すべてが循環して複合的に関わり合うなかで奇跡的に世界が成り立っていることを知っている。そして自らも多様性を表出する一部となり、同時に、世界の多様性を持続することを助けているという意味で二重に役割を担っているのだ。
今私たちはとても不確かな時代にいる。グローバル資本主義が引き起こす経済格差、環境汚染、気候変動、自然災害、エネルギー問題、政治的緊張関係から移民、貧困、孤独まで世界共通の課題は枚挙にいとまがなく、しかもそれらは複雑にからみあい、決して他所の問題とは言えない関わりをもって私たちの眼前に立ち現れる。当たり前だと思っていた価値観をこのまま続けていいものか。それに気づいた人から行動を始めている。依然少数であることに変わりはないだろう。しかし、不確かで複雑で先行きがわからない時代だからこそ、少数のオルタナティブな視点をもった人々が新たな光をもたらすかもしれない。生物は時に脆弱な種や能力も持ち合わせながら生き延びてきた。それは変わりゆく世界で何が生き残る手段に変貌するかわからないからだ。生物多様性を担保することこそが不確かな時代を生き延びる戦略であり、それを知っているのが農とアートなのかもしれない。
(文:天野澄子)
*これは決して慣行農業を否定するものではなく、また自然農に携わる農家がすべてこの通りであるとは限らない。アートやアーティストに対する考え方もここで示すものは一部である。
*1)農林水産省平成25年8月発表「有機農業の推進に関する現状と課題」より
*2)国勢調査 平成27年国勢調査 抽出詳細集計(就業者の産業(小分類)・職業(小分類)など)より
参考文献:
『藝術2.0』熊倉敬聡 著(春秋社)
『発酵文化人類学』小倉ヒラク 著(木楽舎)
取材協力:りんもく舎 http://rinmoku.com/
天野澄子(Sumiko Amano)
横浜国立大学教育学部総合芸術課程卒。1997~2013年まで株式会社タウンアートにてアートプロデューサーとしてパブリックスペースにおけるアート計画の企画から作品設置まで多数のプロジェクトに携わる。2004年文化庁芸術家海外研修によりロンドンのアートNPO「Free Form Arts Trust」にてコミュニティアートについて学ぶ。2013年子育てを機に長野県へ移住。現在は公共文化施設計画の設計支援等、アート思考をOSとしてフリーに活動中。