
ツアー当日、出発場所となっていたアートラボはしもとではS.O.S.のメンバーによる関連企画「SOMETHINKS」展が開催されていた。
「オルタナティブ・スペース」という言葉をあちこちで聞くようになって久しい。一見すると定義がし難いように見えるが、例えば千代田アーツ3331のように、ひとつの場を展示スペースとしてはもちろんのこと、講演会やワークショップ、そしてオフィスや地域住民の集会所など、表現活動に派生した様々なアクティビティを行う場と考えて良さそうだ。
今日、このようなオルタナティブ―すなわち多様な芸術表現を受け入れるための場は、アーティストのみならず市民をも巻き込んで、「アート」の既成概念を拡張する土壌となりつつある。見る/見られる者、表現する者/それを支える者といったあらゆる境界を統合しつつ、時には祭事的な色を湛えながら、オルタナティブ・スペースは開かれた場として芸術と一体化しているのである。
言うまでもないことだが、表現の場をめぐる格闘は20世紀の芸術を語るうえで重要な位置を占めてきた。戦後、物理的・制度的制限のあるホワイト・キューブを踏み越えたアーティストたちが新たな表現の場を模索し、そのムーヴメント自体が社会やコミュニティを生成する役割を担ってきた。例えば、2000年代初頭から日本各地で開催されるようになったアートフェスティバルという形式は、その系譜を受け継ぐムーヴメントと言ってもいいだろう。とある場を舞台に、作品を介して人と人が出会い、関係性を構築する。作品は一連のプロジェクトの仲介役としての役割を果たし、作品鑑賞を含めた「その場での体験」そのものに価値が見いだされる。ニュートラルかつ“鑑賞体験の純粋性”1を志向したホワイト・キューブから、オルタナティブあるいはサイトスペシフィックな場、そしてそれをもとにしたヒト・モノ・コト間の関係性の構築へ————。このような変遷を踏まえて、以下改めてアートと場の関係性について考えてみたい。というのも、先日伺った相模原のプロジェクトが、この文脈において新たな表現の場の「見方」を示唆しているように思われるからである。
SUPER OPEN STUDIO(通称S.O.S.)は、神奈川県北部の相模原で活動するアーティストのアトリエを一般に公開するプロジェクトとして、2013年にスタートした。その制作から展示に至るまでの包括的な活動を作り手自らが組織するムーヴメントとして注目を集めている。アーティストの制作現場における展示というと、例えばヤン・フートが1986年に行った「シャンブル・ダミ(Chambres d’Amis:友人の部屋)展」が挙げられるだろう。ベルギーのゲント市の家々を舞台として、フートと面識のある国際的なアーティスト51人がそれぞれの家で制作・展示を行った画期的なキューレーションである。期せずしてこの展覧会は地元アーティスト主催の展覧会を誘発する効果を生み、オルタナティブ・スペースの代表例として知られることとなった。言わばキュレーターがアーティストの自主展覧会の起爆剤としての役割を担ったわけである。
一方、S.O.S.は相模原に拠点を持ったアーティストが、日頃制作の行われている“実際の”アトリエ(S.O.S.ではスタジオと呼んでいる)を舞台に、キュレーターではなく“彼ら自身の手によって”企画・運営が組織されているという点で、前者とは一線を画している。昨今はTAV GARELLY2やART TRACE GARELLY3など、若手アーティストがひとつの場を基盤として活動するオルタナティブ・スペースが増加しているが、S.O.S.もその一例と言えるだろう。どれも展示活動に派生したアクティビティを、資金調達・運営手法の確立等によって実現可能にしている先例である(左記の過程は、アーティストが自律し、その表現の独立性を保持するためには欠かせないことは言及するまでもない)。
今回、秋季に開催された「スタジオビジット・ツアー」に参加し、計9か所のスタジオを巡った。インターネットで応募した参加者が貸し切りバスに乗って、1日をかけ各スタジオを巡るというプロジェクトだ。今年度S.O.S.に参加しているアトリエは23組、アーティスト数は述べ110人を越える。相模原市の事業として運営されていた2年間を経て、S.O.S.は2015年からアーティストによって組織された団体「Super Open Studio NETWORK」がセルフオーガナイズしている。ツアー参加者は、美術大学に通う大学生、キュレーター、美術愛好者等で、なかにはアメリカのアートフェアから来たという関係者もおり、実に幅広い。貸し切りバス車内の程よい緊張感は、コーディネーターの久野さん(作家であり、「studio kelcova」のメンバー)のお話を聞くうちに和気藹々とした雰囲気に変わり、ツアーは終始和やかなムードで進行した。
相模原は政令指定都市として県内で第3位の人口を有し4、東京都南部との県境に位置するベッドタウンである。関東有数の米軍施設拠点・工場地帯として、また多摩美術大学、東京造形大学、女子美術大学、そして桜美林大学が群立する文教地区としての顔を持ち合わせるこのエリアは、3,40代がその人口の基盤を占める5。その一成員であるS.O.S.のアーティストは、先述した大学の卒業生が多く、それに派生したコミュニティを形成しているようだ。彼らは閉鎖された工場の建物などをスタジオとして再利用し、制作を継続している。衣食住を共にするところもあれば、制作のみ、作品の収蔵庫として使用する人もいるが、ビジネスライクな関係というよりは、たまに食事を共にする友人のような(もちろん家族のようなところもあった)、程よい距離感が構築されているように見えた。

セクシュアリティをテーマにした長尾郁明氏の作品(TANA Studio にて)。ポルノビデオの女性器のイメージをグリッドに還元している。
久しぶりに友人の家を訪ねるような気軽さでスタジオに案内されると、アーティストが茶菓子を用意してにこやかに出迎えてくれた。或いは、こちらに脇目も振らず制作に熱中するアーティストの横を、「目撃者」として通り過ぎる時もあった。総じて言えるのは、画廊や展覧会を見に行く時のような、「見る者」と「見られる者」という明快な境界線がないということである。或いは、非日常としてのキューブのなかで、「作家」や「作品」と対峙する時のような、どこか“特別な”演出も一切無い。彼らはただ「作品を作る人」として、そこで出迎えてくれる。メンバー同士では普段どんなことを話すのか、建物を改装した時のハプニングや、近所の人が差し入れを持ってきてくれたこと、買い出しが少し不便なこと、そしてその延長線上で制作に繋がる自分のエピソードや、作品に込めた思いが紡がれていく。驚くほど自然に、隣人としてのアーティストの本音を聞くことができるのだ。お互いが話し、耳を傾け合うことで、一人ひとりの作家と対等な距離感でコミュニケーションをとることができる。もちろん先述したように、関係者も来ているので、この機会を機に自分を売り込むこともできる。拠点は相模原としつつ、銀座などのギャラリーで発表をする者も当然いる。つまり、あくまで拠点を相模原に置くことのみが共有されているコミュニティなのである。S.O.S.の代表である山根一晃氏はステイトメントのなかで以下のように述べている。「様々なアーティストが異なる目的のもとに集い、同じような風景の下、同じような食堂でご飯を食べる。そして、この相模原という場所をハブとして、各々がめざすものの為にそれぞれが自らの意思と責任のもと動いていく」。6このように、スタジオという場を起点としたメンバー同士のゆるやかで独立した個人からなる連係が、また新たなアトリエ同士の連係を生み、それが地域住民との共同体へと円環状に波及しているのだ。
当たり前のことのようでいて、とりわけ日本の社会では、このようなフラットな関係性のなかでアーティストと対峙することは難しかったのではないだろうか。昨今東京藝大の“特殊性”について取り上げた本が話題となったように、アーティストをどこか別世界の存在として、才能や独創性という言葉で区別してしまう傾向は、未だ確かに存在する。昨今のアートフェスティバルも、地域の持つ自然や建造物、温かな人間関係等とアートの共存を目標とする傾向にあるが、そこに展示される作品は“地域の魅力を引き出すことを目的としたアート”であることが多い。それらが良いか悪いかはさておき、あるテーマをもとに輸入されたキュレーション・プロジェクトであることには変わりない。その点、S.O.S.は、相模原という場を基盤として、まずアーティストがそこに拠点を置くことから始まっている。スタジオを構え、地域の人々と隣人として交流し、生活する延長線上に作品制作がある。アウトリーチの結果としてではなく、自然発生的なエンゲージメントの結果として、アートが緩やかに内在する共同体が形成されつつある。

「pimp studio」にて。自動車修理工場を改装したスタジオで、現在11人のメンバーが集う。
日本のアートプロジェクトは現在、2020年のオリンピックに向け発展の途にある。それは同時に、高齢化に伴う諸地域の過疎化、地方産業の衰退、あらゆる文化施設予算の縮小等、山積する問題の切り札としてのアートが推奨されていることを意味する。官民恊働や国際規模でのプロジェクトは、様々なアーティストを奮起させ上述した危機の打開策となる可能性を持つだろう。しかしその一方で、近現代で議論されてきた先導̶追従の垂直的な構図をなぞる危険を孕んでいることは、既に論じられている通りである。S.O.S.は、先述したステイトメントのなかで、彼ら自身の活動を「アートという場のインフラ整備」だと語っている。明確なオピニオンのもとに集った集団でもなければ、地域おこしのためのプロジェクトでもない。ただひたすらに、異なるアジェンダを持ったアーティストがひとつの場に共存し、静かに、しかし着実に相互関係を構築しているのだ。元来共同体にとって、土地は彼らの“包括的な基盤”7であり、根ざす場なしにその継承は困難であった。土地を拠点とした生産活動を営み、その上で個人としての活動をも並行させる共同体は、中長期的なアートの“インフラ整備”を遂行させる上で重要なムーヴメントとなり得るだろう。その意味において、今日における表現の「場」との関わり方は共同体の命脈を左右する重要なファクターである。大地が肥沃に還るその時こそが、時代の起点となるのではないだろうか。
(文:高橋ひかり)
1 ホワイト・キューブ 現代美術用語辞典ver.2.0 http://artscape.jp/artword/index.php/ホワイト・キューブ
2 専属キュレーターがそれぞれのキュレーションによる展覧会を行うギャラリーとして2014年に始動。展示スペースのほかに、ワークショップやイベント等を行うLAB SPACEを有する。http://tavgallery.com
3 NPO「ART TRACE」を母体とした、両国にスペースを持つアーティストラン・ギャラリー。武蔵野美術大学OBOGの主要メンバーを主軸に、期ごとに参加メンバーを公募、展覧会を主に講演会やワークショップなども行われる。同母体の関連事業としては林道郎著「絵画は二度死ぬ、あるいは死なない」シリーズを出版するART TRACE PRESSなどがある。http://www.gallery.arttrace.org
4 神奈川県の人口と世帯 神奈川県ホームページ…http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f10748/
5 平成27年1月1日現在。…http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/toukei/20998/jinko/nenrei/index.html
6 『SOSBOOK 2016』, p4
7 大塚久雄著『共同体の基礎理論』岩波書店,2000年, p12
高橋 ひかり(Hikari Takahashi)
1995年生まれ。神奈川県出身。武蔵野美術大学芸術文化学科在籍。2014年より絵画制作活動を開始、アーティストランギャラリー・ART TRACE GALLERYにおける個展等7回の出展を経て現在 に至る。アートムーヴメントにおける共同体の自律性・持続性に興味を持ち研究をすすめる。





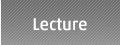





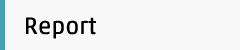





































 他にもTelok Blangah(Ahmad Abu Bakar作、2013)では、鑑賞者が作品制作に関わったシンガポール囚人へカードを書くイベント企画が付いている。もともとこの作品は何千もの瓶でいっぱいの木船(コレックkolekという)の作品だ。それぞれの瓶にはシンガポール人の囚人たちが書いたメモが入っており、彼らは自分たちの願いや希望を自分たちの民族の言葉で書き留めている。多民族が暮らすシンガポールではメモに書かれる言葉が違う。そのため木船がそのエスニックルーツを示唆し、さらに木船に何が積まれているかも関心の的となる。鑑賞者は囚人に宛てたメッセージや質問によって繋がりを意識し、作品理解やその意味を一層深めるのだ。
他にもTelok Blangah(Ahmad Abu Bakar作、2013)では、鑑賞者が作品制作に関わったシンガポール囚人へカードを書くイベント企画が付いている。もともとこの作品は何千もの瓶でいっぱいの木船(コレックkolekという)の作品だ。それぞれの瓶にはシンガポール人の囚人たちが書いたメモが入っており、彼らは自分たちの願いや希望を自分たちの民族の言葉で書き留めている。多民族が暮らすシンガポールではメモに書かれる言葉が違う。そのため木船がそのエスニックルーツを示唆し、さらに木船に何が積まれているかも関心の的となる。鑑賞者は囚人に宛てたメッセージや質問によって繋がりを意識し、作品理解やその意味を一層深めるのだ。













































